解雇されるのは労働者の責任?~不当解雇について

一生懸命働いてきたつもりだったのに、ある日突然、解雇宣告を受けた。
会社が言うには自分に能力が足りないという。
自分の努力が足りなかったのかもしれない。諦めるか……。
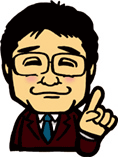
まじめで責任感の強いあなたは解雇宣告を受けた時、こんなことを思ったかもしれません。
でも、あなたの受けた解雇は、あなただけの責任なのでしょうか?
そもそも能力を理由にした解雇は正当なのでしょうか?
昔から日本では、労働者が使用者に比べ、立場が弱かったことがありました。
その歴史をふまえて現在の法律は、労働者を守ることを優先に考えられています。
労働者を解雇する立場にある使用者が不当に解雇権を濫用するのを防ぐために、一定のルールが設けられているのです。
就業規則に書いてあるからといって解雇が正当とは限りません
例えばこんな社員がいるとします。
仕事のミスが多く、上司から注意されることが多い。
顧客からの苦情が寄せられることがよくある。
仕事へのやる気や協調性も見られない。
使用者である会社は、こうしたことを理由に、解雇を宣告することがよくあります。
そしてその根拠を就業規則に求めてくるようです。
確かに会社の就業規則の多くには、
- 「労働能率が著しく劣る場合は解雇できる」
- 「勤務成績が著しく不良な場合は解雇できる」
などという記載がよく見られます。
しかし、就業規則にこう書いてあるから、ということだけを根拠に、この社員を解雇することはできません。
実際の裁判所の判断
裁判の判断では、「就業規則に『労働能率が著しく劣る場合は解雇できる』という規則があったとしても
能力が平均的なレベルに達していないだけでは解雇することはできず、『著しく能力が劣り、しかも向上の見込みがない場合に限って認める』べきとしています。
就業規則に「勤務成績が著しく不良な場合は解雇できる」という規則があるからといって
営業成績が悪いだけで解雇することはできず、『会社の経営や運営に支障や損害が生じている、または重要な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っている』ことが必要です。
[su_note note_color="#FFFFFF" id="00″]
コラム:あいまいな「能力不足」という基準
 能力不足と一口に言っても、どこまでが許容されるレベルで、どこからがそうでないか、人によっても違いますし、明確な基準を設定することができません。それだけ「能力不足」という言葉は、主観的で抽象的です。
能力不足と一口に言っても、どこまでが許容されるレベルで、どこからがそうでないか、人によっても違いますし、明確な基準を設定することができません。それだけ「能力不足」という言葉は、主観的で抽象的です。
[/su_note]
[su_note note_color="#FFFFFF" id="01″]
コラム:「能力を向上させる責任」は労働者?
 日本では、「仕事の能力を向上する責任を負っているのは社員である。だから能力不足の責任は会社ではなく社員にある」
日本では、「仕事の能力を向上する責任を負っているのは社員である。だから能力不足の責任は会社ではなく社員にある」
と考える会社が多いようです。
しかし、本来、日本における職能資格制度では、労働者の能力向上やスキルの開発は、会社が教育や配置転換をするのが基本とされているのです。
ほとんどの会社では人事権は会社が握っており、社員が自分の意志で担当や部署を変わったりすることはできません。
その人に向いている仕事が他の部署にあったとしても、自由にそれを選ぶことはできないものです。
ですから、社員の能力不足が見受けられたなら、会社はそれ相応の研修や、その社員の適性に合った仕事への配置換えをすることに努める責任があるとされているのです。
にもかかわらず、社員の能力の向上のために何も対策を講ずることもしないで、就業規則に書いてあることだけを根拠に社員を解雇することは、無効となり、不当解雇となります。
 もっとも、会社が労働者に対して能力開発の機会を与え、しかも使用者の押しつけではなく労働者の意見や適性も取り入れるなどして、相当の期間をかけて努力をしていたとします。
もっとも、会社が労働者に対して能力開発の機会を与え、しかも使用者の押しつけではなく労働者の意見や適性も取り入れるなどして、相当の期間をかけて努力をしていたとします。
もしも労働者側がこれに真面目に取り組まずこの機会を生かすことができなかった場合には、能力不足だけではなく、他の解雇事由(勤務状況が著しく不良で改善の見込みがない、協調性が著しく劣る、勤務態度が不良等)にも該当することも多いと考えられます。
いずれにしても、能力不足により労働者を解雇する場合には、会社側に相当な努力と慎重な判断が要求されるようになっています。
[/su_note]
ご相談内容
相談者は4か月の試用期間中に明確な理由も提示されないまま解雇の通告を受け試用期間の満了に伴い解雇されました。
前提試用期間中の解雇について判例は?
試用期間中の解雇であっても、判例では
「解雇権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とされています。
「解雇は無効である」と主張
そこで、会社に対して内容証明で解雇は無効であり、相談者は労働者の地位にあることを主張するとともに他方で、会社側で解雇を撤回したうえで合意退職に向けた話し合いを希望するのであれば、条件次第では合意退職に応じても良いと通知をしました。
会社側の主張
これに対して、会社からは、労働契約の締結に当たって、相談者の知識やキャリアなど熟練度の高い労働能力などが特に措定され、賃金もそれに見合った額で合意したこと職務の処理状況も悪く、指示に従わないとともに、勤務態度も不良であることから、解雇は有効であるとの回答がありました。
労働審判を提起して主張
そこで、労働審判を提起して、こちらからは、上記①、②のような事実はなく、特に、相談者の勤務状況には問題がなかったことを丁寧に主張しました。
裁判所による審判の結果
その結果、第1回目の労働審判において裁判所からこちらの主張を全面的に認めたうえで、
和解案として、解決金180万円の提示があり和解が成立しました。
勝訴のポイント
この事件は、労働審判となりましたが、第1回目の期日で、こちらの主張を全面的に認める内容で解決をすることができました。
労働事件は相談後、早い対応が必要である場合が
多く、丁寧かつスピーディな対応を心掛けています。
特に、労働審判では、第1回目の期日前に、事前の準備を十分にしたうえで、こちらの主張をしっかりと丁寧に行い、早期かつ有利な解決を目指すことを心掛けています。
ご相談内容
相談者は40歳代の男性。期限の定めのない雇用契約で,営業職で働いていた会社から,2ヶ月分の給料を支払うことを条件に,翌月からの労働契約の解消を一方的に言い渡されました。
会社は,この相談者について,営業職の仕事がなくなり,他の職種に配転することも検討したが,それも難しいということを理由としていました。
解決の方針・結果
会社の労働契約の解消というのは,整理解雇の要件を満たしていないとともに,仮に退職勧奨であったとしても,労働者である相談者はそれに合意をしていない以上,法的には無効なといえるものでした。
ただ,このケースでは,相談者が,このような会社では戻っても嫌がらせなどを受ける恐れもあり,会社には戻らずに,一定の金銭をもらって早期に退職したいという希望がありました。
そこで,会社に対して,内容証明で,解雇は無効であり,相談者は労働者の地位にあることを主張するとともに,他方で,会社側で解雇を撤回したうえで,合意退職に向けた話し合いを希望するのであれば,条件次第では合意退職に応じても良いと通知をしました。
会社と何度も交渉した結果,最終的には,会社側が給与の約5ヶ月分を解決金として支払うこと,会社都合の退職とすることを条件に,退職をすることで合意が成立しました。
相談後,約1か月足らずでのスピード解決となりました。また,会社都合の退職のため,すぐに失業手当も受給できました。
労働事件は,相談後,素早い対応が必要である場合が多く,丁寧かつスピーディな対応を心掛けています。
また,労働事件は,長引くことが依頼者の利益には必ずしもつながらないことも多いため,依頼者の立場に立って会社との交渉で早期の解決を図ることも大切だと考えています。
不当な解雇に遭ったら、まず弁護士に相談。
労働者個人が会社組織を相手に交渉をすることはエネルギーと精神力の要ることですし、まともに相手にされなかったりすることもあり、現実には難しいと思います。
そんなときに弁護士は、あなたの味方となって会社と交渉します。
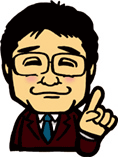
解雇をめぐって会社を相手にするときは、経験と専門的な知識のある弁護士があなたに代わって交渉することが大きなメリットとなります。




