職場のパワハラと労災について

職場の上司の「パワハラ」により、うつ病を発症した場合やうつ病を発症したのちに自殺した場合に、労災として認められるのでしょうか。
厚労省の労災認定基準に「パワハラ」が追加
2020年5月末、厚労省は「精神障害に関する労災認定の基準」を改定し、新たに「パワハラ」の項目が追加しました。
(参考リンク)厚労省ホームページ「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
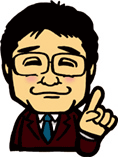
このパワハラの項目を追加した労災認定の基準は、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の施行に合わせて、2020年6月より適用されています。
精神障害の労災認定基準では、「業務による心理的負荷評価表」というものが用いられますが、この評価表の中に、「出来事の類型」「具体的出来事」という項目があり、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」といった内容の項目が追加されています。
では、上司からのパワーハラスメントによって、部下が精神障害を発症してしまった場合には、どのような基準で労災認定されるのでしょうか。
それを知るためには、まず「パワーハラスメントの定義」について知っておく必要があります。
パワハラの定義
まず、労働施策総合推進法により、職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たす言動とされています。
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 就業環境が害されるもの
次に、精神障害の労災認定基準は、行為がもたらす心理的負荷(ストレス)を「弱・中・強」の3段階で評価しており、パワハラ労災の基準も同様に「具体的出来事」が3段階で評価されることとなっています。
こうした中で、厚生労働省の「精神障害の労災認定に関する専門検討会報告書」では、パワハラと心理的負荷の程度の具体例が示されています。
パワハラの具体例とパワハラに対する法的責任に関して下記の記事で詳しく解説しています。
心理的負荷が「強程度」と評価される具体例
- 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
- 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
- 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
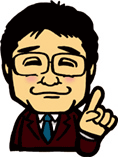
具体的には……
・人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃。
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
…などがあります。
- 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
「上司以外」の同僚などからのいじめと労災との関係は以下の記事をご覧ください。
心理的負荷が「中程度」と評価される具体例
上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない場合
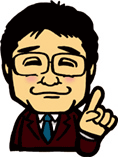
具体的には……
・治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃
・人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃
・必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
…などがあります。
心理的負荷が「弱程度」と評価される具体例
上司等による「中」に至らない程度の身体的攻撃、精神的攻撃等が行われた場合とされています。
そして、うつ病など精神障害を発病した場合に、発病前おおむね6か月間の状況についての心理的負荷の総合評価が「強」と判断される場合は、業務以外の心理的負荷などがなければ、業務上のものと判断されることとされています。
また、業務による心理的負荷によって、「うつ病や重度ストレス反応等の自殺念慮が出現する精神障害」を発病した者が自殺を図った場合は、業務起因性を認めるとされています。
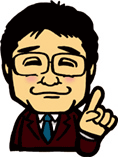
すなわち、心理的負荷が「強」と判断されるパワハラにより、うつ病を発症した場合やうつ病を発症したのちに、自殺した場合には、労災として認められることとなります。
パワハラによるうつ病など労災を巡る法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
平成25年当時、労働者と使用者間のトラブルを扱う全国の労働局の「個別労働紛争解決制度」に寄せられた職場の「いじめ・嫌がらせ(パワハラ)」に関する相談が、平成25年度は5万9197件となり、過去最多を更新したとの報道がありました。
労働トラブル全体の相談は、24万5783件で平成24年度より3.5%減ったようです。
集計によると、パワハラにまつわる相談は、前年度比14.6%増で、「解雇」や「自己都合退職」にまつわる相談を上回り、最も多かった。
相談には、上司から「仕事が遅いくせに、飯を食うのだけは早いな」「ばか野郎」などと繰り返し暴言を受けた事例や、契約社員が支店長から「ミスを3回したらクビだ」と言われて精神的に追い込まれた事例などがありました。
また、「死ね」「口答えするな」などの強圧的な言葉や、「俺に従わなければ出世できない」「お前はいらない」など人事権を振りかざす暴言も見られたり、頭をたたく、後ろから蹴るなどの暴力もあり、精神疾患になったり、退職に追い込まれたりする例もありました。
最近、当事務所でも、職場での暴言などのパワハラや退職強要などの相談が増えていますが、このような行為は、まじめに働いている労働者の権利を侵害するもので、法的には許されるものではありません。





