長時間労働による脳・心臓疾患と労災について
脳梗塞・心筋梗塞と労災の関係
皆さんは、労災といえば、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
まず、最初に思い浮かぶのは、工場などの作業現場での事故だと思います。
また、通勤途中で交通事故などに遭った場合も労災になることも、多くの方は知っていると思います。
では、仕事が忙しくて残業が多い生活を送っている中で、脳梗塞や心筋梗塞で職場や自宅などで倒れた場合はどうでしょう。

このような場合、多くの方は、もともと高血圧、高脂血症、肥満などの生活習慣病があったことを原因として、片付けてはいないでしょうか。
一般に、長時間の残業があったとしても、多くの場合は、仕事で忙しいのは仕方ないとか、みんなも一緒だけど、他の人はなっていないということで片付けられがちです。
また、このような長時間の残業をする方は、まじめで仕事が好きだということ、自分から進んで仕事をしていたということも影響していると思います。
しかし、発症前の数ヶ月間以上、長時間の残業が続いている中で、脳・心臓疾患を発症した場合には、労災が認められる可能性が十分にあります。
脳・心臓疾患の労災の認定基準

厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準を定めています。
以下では、その基準のうち、「脳・心臓疾患」とは何か、認定基準の考え方と3種類の認定要件、長時間労働との関係について簡単に説明したいと思います。
1.脳・心臓疾患とは(対象疾患)
脳血管疾患・・・・脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、 高血圧性脳症
虚血性心疾患等・・心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む) 、解離性大動脈瘤
2.認定基準とその基礎
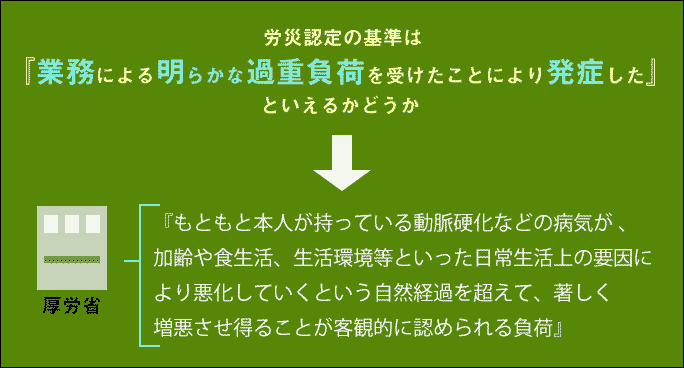
労災認定の基準は、『業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した』といえるかどうかという基準で認定されます。
一般に、脳・心臓疾患は、加齢、食生活、生活環境等の日常生活による様々な要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、あるとき突然に発症するものです。
この『過重負荷』については、『もともと本人が持っている動脈硬化などの病気が、加齢や食生活、生活環境等といった日常生活上の要因により悪化していくという自然経過を超えて、著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷』と定義されています。
もう少しわかりやすくいえば、
・普通の日常生活を送っていたら、そこまで悪化しなかった。
・業務によって明らかに悪化した。
…と言えるかどうか,ということです。
3.具体的な要件
『業務による明らかな過重負荷』にあたるかどうかについては,
- 発症直前から前日までの間に,事故や災害などの「異常な出来事があった」
- 発症の直前の1週間程度に,「短期間の過重業務に就労した」
- 発症前の概ね6か月の期間に,「長期間の過重業務に就労した」
という3つの認定要件を設けており、①~③のいずれかに該当すれば、業務と発症との関連性が強いと評価されます。
そして、脳・心臓疾患の労災では、③の認知基準が問題となることが多く、「長期間の過重な業務に就労した」かについては、労働時間が重要なポイントとなります。
労働時間の評価の目安
具体的には、
㋐発症におおむね100時間
又は
㋑発症前2か月間ないし6か月間にわたって,1か月当たりおおむね80時間
を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が高いと評価されています。
そのため,㋐又は㋑の時間外労働が認められる場合は、労災認定される可能性が高くなります。
例えば,発症前2か月間の1か月当たりの時間外労働がおおむね80時間を超えていれば,㋑の基準を満たすこととなります。
なお 、業務の過重性の判断に当たっては 、「不規則・拘束時間の長い勤務」、「出張の多い業務」 、「交替制勤務・深夜勤務」 、「作業環境」 、「精神的緊張を伴う業務」など、 労働時間以外の要因も検討されることとなっていますが、労災の認定の実務では、労働時間、すなわち、上記の㋐又は㋑の基準を満たすかどうかが重視されており、それ以外の要因は、㋐又は㋑の基準を満たさない場合に、検討や考慮されるという取扱いとなっています。
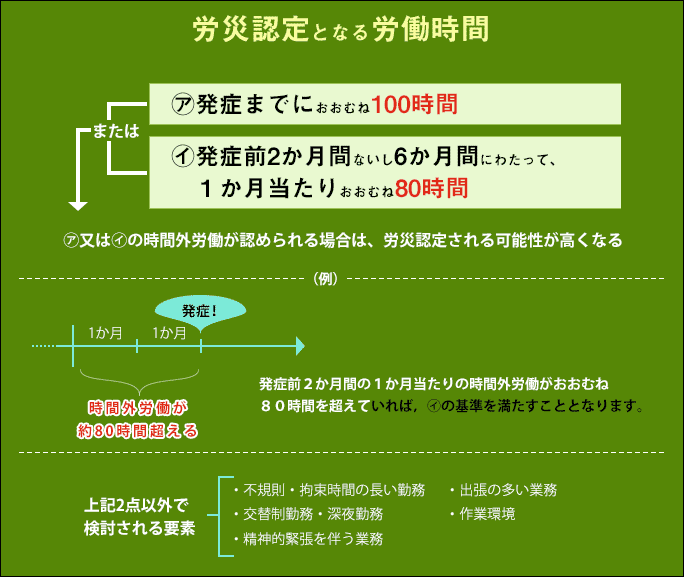
生活習慣病を持つ労働者が長時間残業で倒れた場合も,労災が適用できる?
では,脳梗塞や心筋梗塞で倒れた労働者が,もともと生活習慣病を持っていた場合はどうでしょうか?(職場で倒れたか,自宅で倒れたかを問いません)

発症前の数ヶ月間以上、長時間の残業が続いている中で,脳・心臓疾患を発症した場合には、労災が認められる可能性が十分にあります。
このような場合,多くの方は,もともと持病があったことを理由に,私病として片付けてはいないでしょうか。
仮に,高血圧や高脂血症などの生活習慣病を持っていたとしても,それまで通常の生活をしており,発症の主たる要因が長時間残業と認められる場合は,労災と認定されます。
労災の可能性があることに労働者も会社も気づかない
しかし持病を持った労働者が,脳や心臓疾患などで急に倒れた場合,労働者も,会社も「労災にあたる」という発想にはなりにくいのです。
「長時間の残業があったとしても仕事として仕方なかったのだから、健康保険の傷病手当金の支給手続きをして済ませるしかないだろう」
「長時間の残業をするほど,まじめで,仕事が好きだ(自分の意志だった)」
「一緒に働いている同僚たちは病気になっていないのだから,自分の身体に原因があるのだろう」
…など、労災とは無関係な処置をして済ませてしまうことも多いのです。
持病(私病)か?労災か?

このように,日本では一般に労災に関する知識がないため,脳や心臓疾患などで倒れた多くの方が労災ではなく健康保険の傷病手当金の手続きだけで済ませられていることが多いのです。
しかし,脳や心臓疾患などが原因で身体に後遺障害(半身不随など)が残れば仕事ができなくなりますし,一定期間が経過すれば,会社から解雇されてしまいます。
もしそうなったとき,単なる持病(私病)として扱われる場合と,労災として認められる場合では補償内容に雲泥の差があります。
こんなに違う持病(私病)と労災の補償内容
| 持病(私病)として扱われる場合 | 労災として扱われる場合 | |
|---|---|---|
| 給付制度 | 健康保険からの給付 | 労働基準法の「災害補償」労働保険法による「災害補償(保険給付)」 ・国から支給される最低限度補償 ・労働者の過失は問われない |
| 治療費 | 健康保険で3割を自己負担 | 全額が療養給付として支給される |
| 支給期間 | 健康保険から傷病手当金として1年6か月 | 療養に必要な期間中 |
| 支給金額 | 給料の2/3が支給される | 給料の8割が支給される |
| 障害が残った場合 | 障害年金が支給される | ・障害年金 ・労災の障害補償給付 |
| 解雇 | 会社に病気休暇の制度がない場合は,有給を使い果たすと,療養中であっても解雇される可能性がある。 ↓ 障害が残った場合は退職金をもらって退職せざるを得ない | 療養中は労働者を解雇することは禁止 |
確かに労働者は持病を持っていたかもしれません。
でも,倒れた直接の原因が長時間残業などの「働きすぎ」であるならば,労災が適用されるのです。
こんなときは弁護士に相談しましょう
労災の分野において、特に次のようなことでお困りの場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
持病か、労災か?判断できない
これまで書いてきたように,脳・心臓疾患で倒れた労働者が、長時間残業が続いていたのであれば、たとえ元々持病をもっていたとしても、労災が適用さ入れる可能性が検討できます。
しかし、これを医学知識や経験の無い方が自分で判断したり、労働との因果関係を証明するのは困難です。
こんなときは、数多くの労働問題に対処してきた神戸山手法律事務所の弁護士に相談しましょう。
会社が労災申請に対して非協力的
会社によっては、労災の発生を元請会社や労働基準監督署などに知られることを嫌がる、もしくは、問題が大きくなることを嫌がるあまり、労災申請手続などに協力しなかったり、労働者だけに責任があるかのように報告したりすることがあります。
また,労災のうち、過重な労働による脳・心臓疾患の発症やパワハラによるうつ病の発症などについて、会社が労災の申請を積極的に行うことはほとんどありません。
身体的、精神的な負担を避けるためにも,このような会社に対し、病気を患った労働者が個人で立ち向かうことはせず、神戸山手法律事務所の弁護士に相談してください。
会社へ損害賠償,慰謝料の請求をしたい
労災が認定され、長期間入院や通院を余儀なくされてしまった労働者は、後遺障害が残ったとしても、その精神的損害に対する慰謝料 (入・通院の慰謝料,後遺障害の等級に応じた慰謝料,逸失利益など)までは補償されません。
また,会社に落ち度がある場合には損害賠償の請求権が発生しますが、労働者から請求することなく会社から進んで損害を補償してくれることは,まずありません。
このように労災で補償されない範囲に関しては,民事上の損害賠償を請求する必要があります。
損害賠償請求の手続きは、やはり専門的な知識が必要となるため、弁護士への依頼なくして進めることはできません。
自殺,脳・心臓疾患による過労死の疑いがある
労働者が過重な労働を重ねた結果、うつ病で自殺したり、心臓や脳疾患で死亡した場合に、遺族の方が「過労死ではないか」と悩んだりしている場合にも,神戸山手法律事務所の弁護士に相談してください。
お気軽にお問い合わせください。

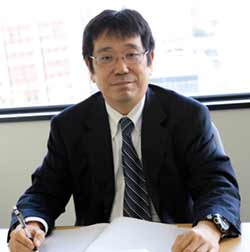 神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)